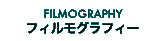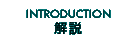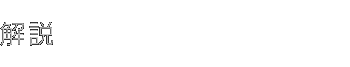自動機械の恍惚
西嶋憲生(映像研究者)
伊藤高志(1956年福岡に生まれ、現在は京都在住)は、日本を代表する実験映画作家の一人である。彼は九州芸術工科大学の芸術工学部を1983年に卒業したが、在学中の1981年にほとんどデビュー作と言っていい『SPACY』で作家として登場し、その問題意識と完成度の高さはすでに早熟な巨匠を思わせていた。この作品のサウンドを担当した稲垣貴士(洋祐)も同級生で映画・音響作家である。
『SPACY』は約700枚の連続したスチル写真を再撮影した作品で、その視点(カメラ)の動きが直線運動から円運動や放物運動へ、また水平の動きから垂直な動きへとスピーディに変化していく。計算されつくした絵コンテに従い1枚ずつ大学の体育館で撮影されたという。
連続写真を動画的に再構成するという手法自体は、松本俊夫(当時、九州芸術工科大学で彼の指導教授だった)の『アートマン』(1975)や居田伊佐雄の『オランダ人の写真』(1976)といった70年代半ばの日本の実験映画にすでに見られ、伊藤高志はそれらの直接的な影響もうけている。だが一方で、彼の編み出したスタイルはより洗練され、より複雑で、完全に新しいものでもあった。
たとえば『アートマン』で円運動をくりかえすカメラの被写体となったのは椅子に座り能面をつけた人物だったが、『SPACY』ではその位置に写真(映像)それ自体がある。これはラストショットでカメラと撮影者(作者のセルフポートレイト)を写していることと共に『SPACY』が内に秘めているself-reflexive(自己言及的・自己反省的)な側面を暗示するひとつの要素にほかならない。『オランダ人の写真』の平面性(写真の二次元性)とフリップブック的な運動のイリュージョンと比べた場合にも、『SPACY』にはフレーム内フレームヘの侵入感覚やダイナミックな運動感、そして空間的広がりがあり、そのサウンドと共に幻想映画(fantastic film)としての側面を明らかにしているのである。
伊藤高志は1984年にこう書いたことがある。「映画は非現実的な世界をそれ自体が生々しい現実として知覚され、独特の不思議な空間を作り出すことが出来るものだ。私はこの映画の魔術を駆使し、今まで慣れ親しんで見てきた日常的風景がドキッとする“一瞬”をキッカケに、見る者(私)を超常現象的なイリュージョンの渦へ引き込む過程を、映像に求めてゆくことを最大のテーマにしている。」(「月刊イメージフォーラム」1984年10月号、「マイ・フレーム」)
この彼特有な嗜好は『SPACY』にもよく現れているといえる。同時に、観客たちが魅惑されたのは、コンピュータ制御のように“自動的”に動いていくカメラのスピード感でもあった。人間の感覚や論理を超えて自律的に動き続ける自動機械の恍惚。そして、映像を所有したり支配するのではなく、その「中に入りたい」という作者の抑えがたい欲望。
その恍惚と欲望は彼の全作品に共通するものであり、連続写真の再撮影とは別の系列の彼のフィルム、『THUNDER』(1982)、『GHOST』(1984)、『GRIM』(1985)などバルブシャッターとコマ撮り撮影によるオカルト的な実験“ホラー”映画(そこでは光が亡霊となって空間をかけめぐる)にも一貫する。
この2つの系列で伊藤高志はすでに20本以上に及ぶ16ミリ、8ミリ、ビデオの作品を作ってきたが、近年の傑作『THE MOON』(1994)や『ZONE』(1995)において、「夢と記憶」というモチーフの中で2つの系列は統合されつつあるといえる。
付記——本稿は、パリのジョルジュ・ポンピドゥ国立芸術文化センター(ポンピドゥセンター)が1995年に『SPACY』(目録番号f6 1299)を購入し、その翌年同館の実験映画コレクション・カタログとして500ページ近い『動きの芸術(L'art du mouvement)—ポンピドゥセンターの映像コレクション1919-1996』(ジャン=ミシェル・ブウール編、エディシオン・デュ・サントル・ポンピドゥ、1996)を出版した際に依頼されて書いた"Takashi Ito"の日本語訳に若干の加筆をしたものである。(筆者)
伊藤ワンダー高志ランド
かわなかのぶひろ(映像作家)
人生にはさまざまな出会いがある。自分の一生を決定してしまうような人との出会い。作品との出会い、なかんずく時代との出会い…。
映画に関しては単に熱狂的な観客にすぎなかったぼくが、自分で作品を手がけるようになったのは、たまたま手に取った映画の小冊子にジョナス・メカスが「自分でやらなきゃ駄目さ!」と書いた文章が目に飛び込んできたからだった。これが英国の「サイト・アンド・サウンド」誌に発表されたのは1959年だが、その翌年に早くも翻訳されたということも、出会いにとっては大きな意味をもっていた。
8ミリが一般的ではなかったそれ以前に出会っても、メカスがもてはやされるようになった以降に出会っても、これほど深いつながりにはならなかったろう。そしてその時、たまたま8ミリカメラが入手できる時代だったということも決定的な要因であった。
出会いにはどうやら、自分が望んでいるだけではどうにもならない絶妙なタイミングがあるようだ。それがグッド・タイミングになるか、バッド・タイミングになるかは誰にも分からない。
外国の美術館で、コレクションの対象としてひっぱりだこといっても過言ではない人気の映像作家、伊藤高志のそもそものスタートも、どうやらこの摩訶不思議なタイミングにあるようだ。
手元に届いた自筆のプロフィールによると、伊藤高志は幼少のころからマンガを描くのが趣味だった。石森章太郎の「サイボーグ009」に自分なりのストーリーをあてはめてノートー冊ぶん描きあげたり、さまざまなマンガ家のキャラクターを引用して、いわばオールスター・キャストによる長編怪獣マンガを手がけたりしていたようである。
そんなマンガ少年が実験映画を手がけるようになったキッカケは、九州芸術工科大学に入り、卒業制作の指導教官として松本俊夫と出会ったからにほかならない。もちろんそれ以前にも、福岡の実験映画上映組織〈F.M.F.〉との出会いがあり、そこでは処女作の『時空』(1977年)をはじめとする5本の8ミリ作品を発表していた。そうした時期に、たまたま日本の実験映画の第一人者である松本俊夫が、芸工大の教授として九州に招かれ、大学5年生の伊藤高志の卒業制作指導教官として担当するという巡り合わせがなければ、伊藤高志はあるいはもっと別の道を歩んでいたのかも知れない。松本俊夫によると、当時、伊藤高志の卒業制作を指導しようという教官が誰もいなかったそうである。それならば、と新任の松本俊夫が担当したという。
また、その時期に、後に『SPACY』となる作品に直接的な影響をおよぼしたと考えられる松本俊夫の『アートマン』(480箇所のピン・ポイントから撮影された静止画像がめくるめく円運動を描き出すスチル・ムービーの試み)や、居田伊佐雄の『オランダ人の写真』(渚を歩く足の連続分解画像が、写真の中の写真といった合わせ鏡状に連鎖してゆく)が完成していなければ、伊藤高志のデビューはもっと後になっていたかも知れない。
『SPACY』を最初に観たのは1981年のイメージフォーラム・シネマテークだった。700枚にもおよぶ連続写真があたかもジェットコースターのようなムービング・イメージを紡ぎ出すこの伝説的な作品は、『アートマン』や『オランダ人の写真』といった先達があることを知っていても充分驚嘆させられた。その技術や方法は先達の直接的な影響下にありながら、さらに洗練されたムービング・イメージとしてわれわれの眼前に出現したのである。まさに衝撃的なデビューだった。
伊藤高志のデビューは、先達と後進が互いに影響をおよぼし合う日本の実験映画の特質を鮮やかに体現している。これがヨーロッパやアメリカになると、作家間の交流はあっても、作品上で互いに影響しあうということはほとんどみられない。アイ・アム〜からスタートするメンタリティが他者の影響を拒絶するのか、オリジナリティという呪縛がそうさせるのか…。
伊藤高志がもしも西欧社会でデビューしたとしたら、こういう評価は得られなかったかも知れない。
『SPACY』で忘れられないのは、1984年にこの作品が当時はまだ西ドイツと呼ばれていたドイツの〈オスナブリュック実験映画ワークショップ〉に招待されたときのことである。フランスのイェールと並んでヨーロッパでは最大の実験映画祭と称されていたオスナブリュックで、この作品が投げかけた衝撃は、日本でのデビューに勝るとも劣らないものだった。
オスナブリュックは、ケルンから特急で2時間あまりのオランダ国境に近い小都市である。日本のガイドブックには駅名のインフォメーションしか載っていない。そんな田舎町で、世界でも有数の実験映画祭が開催され、ヨーロッパ中から200名あまりの映像作家たちがつめかける。山小屋風の倉庫といった外観の会場内は、真冬というのにつめかけた観客の熱気でむんむんしていた。
ドイツ人は時間に正確だと聞いていたけれど、このフェスティバルでは作品の上映前後に、出品した作家のスピーチ・タイムがあるため、この日の上映は遅れに遅れていた。日本の作品の最初アンソロジー・ロールが終わったときは、とうに夜半を過ぎていて、当日のトリを務める予定だったルツ・モンマルツの長編作品が繰り上げて上映されることとなった。終電の時間を考慮してそういう決定になったのだが、当日の目玉が上映された後に残りのロールを上映するということには、いささか抵抗があった。終電で観客がみんな帰ってしまうかも知れない。
ところが、である。トリが終わっても観客は誰ひとり帰ろうとはしなかった。日本の実験映画の質の高さが、観客の問ですでに密かな評判になっていたのだ。したがって最後のロールも拍手に次ぐ拍手の連続だった。そういう雰囲気の中で伊藤高志の作品がはからずも大トリとして上映されることになったのだ。
『SPACY』が終わった瞬間、一瞬の沈黙。やがて万雷の拍手が会場を割れんばかりに揺るがした。成功だった、大文字の成功だった。
そのあまりの反響に一瞬ぼ〜っとしてしまったが、まだスピーチが残っていることを思い出してステージの方へと人波をかきわけた。と、ステージではすでに誰かがスピーチを行っている。
「これはね、写真でつくったんだ。写真なんだよ!」と、この作品の技術を、口角泡をとばしながら説明している人物がいる。ぺ一ター・ヴァイベルというウィーンの実験映画ではちょいとうるさがたの大学教授だった。彼の興奮は痛いほど分かる。水をさすにしのびなく、まるで自分の作品であるかのように語っている彼のスピーチに、しばらく聞きいることにした。
日本の実験映画がまとまったかたちでドイツで公開されるのは1972年以来のことだった。当時まだ健在だった寺山修司の勧めで、ミュンヘン・オリンピックで公演する「天井桟敷」と同行したイメージフォーラムの富山加津江が、ミュンヘンとベルリンで日本の実験映画を公開していた。あれから12年。今回はオスナブリュックを振り出しに11の都市での連続巡回上映。しかも伊藤高志のような大型新人の作品を携えて…。
感慨もひとしおだった。ベルリンではベルリン映画祭でお馴染みのキノ・アルズナールで上映した。フランクフルトではのちに映画博物館になるコミュナーレス・キノ、フライブルグでは駅舎を改造した映画館、シュツットガルトの会場はプラネタリウムの中という豪華版…。
ヴェルナー・ネケスを訪ね、彼がそのときラッシュの状態で見せてくれた、後に『フィルム・ビフォー・フィルム』となる作品と出会ったのも、W&B・ハインの自宅で上映し、酒蔵が空になるまで呑み、そして語りあったのもこのときだった。
なかでもとりわけ印象深かったのがヴェルツヴルグの造形大学での上映だった。オスナブリュックでの上映に参加していた学生たちが、日本の作品の質の高さを、そして『SPACY』の衝撃を、学内で自主的に宣伝してくれたせいもあって、会場に充てられた教室は立錐の余地もない盛況。もちろんここでも『SPACY』は予想以上の熱気で迎えられた。上映後に教官がカンパの帽子をまわしたところ、少額紙幣ながらみるみる山になったほどである。こういう出会いのひとつひとつが、まるで宝石のように輝いて泛かんでくる。創造するものたちの至福の瞬間だ。
伊藤高志のその後の驀進は、いまさらふれるまでもないだろう。『SPACY』で究めたスチルによるアニメーションをさらに洗練させた複雑なムービング・イメージを手がける傍ら、実景をバルブ(タイム・エクスポーズ)撮影することによって生み出される奇妙な空間造形——そこでは光が一連の帯になり、人間はブレてゴーストのような存在になる…。
とりわけ最近の作品では、それらの組合わせがより精密に、より複雑になり、いったいどこからどこまでが実写でどこがスチルなのかが判然としないワンダーランドをかたちづくっている。映像を手がけたことのある人間なら、その撮影手続きのこみいり方にただただ圧倒されるだろうし、そうした技術に無縁の観客にも、日常の光景がみるみる異常な世界にひきこまれるこの視覚効果に魅了されてしまうことだろう。